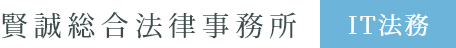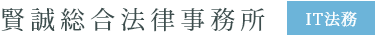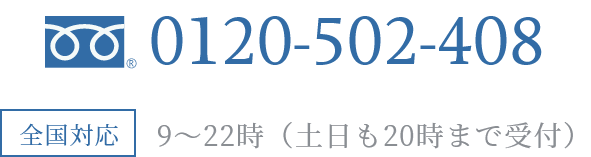グレーゾーン解消制度を利用する際の要点
- グレーゾーン解消制度
弁護士: 岡田信吾
第1 はじめに
近年、情報通信技術の急速な発展により、事業分野を問わず、これまでになかった新たなサービスが次々と登場しています。特にコロナ禍以降、IoTを駆使した新たなサービスの開始を検討する機会が増えたという企業様も多いのではないでしょうか。
新たなサービスを開始する際、必ず検討しなければならないのが、その事業に対する規制の有無です。しかし、技術の進歩が急速であるために、現行の規制法が想定していない事業やサービスが生まれることもあります。そのような場合に、その事業やサービスが、現行の規制法の対象かどうか不明なままでは、事業を進められず、ビジネスチャンスを逃すことになりかねません。
そこで、産業競争力強化法7条1項では、事業者が新しく開始する事業における規制の解釈・適用の有無を確認できる制度として「グレーゾーン解消制度」を設けています。
第2 グレーゾーン解消制度の概要
1 確認対象となる「新事業活動」
「新事業活動」とは、①新商品の開発又は生産、②新たな役務の開発又は提供、③商品の新たな生産又は販売の方式の導入、④役務の新たな提供の方式の導入、⑤新たなビジネスモデルの採用や生産工程の高度化などその他の新たな事業活動、をいいます。
たとえば、同じ業種で行う新役務の提供であっても、質が異なることにより利用目的、提供経路等が異なる新たな役務を提供することは、②新たな役務の開発又は提供にあたります。
新事業活動であるかどうかは、その申請者を基準に判断されます。つまり、すでに世の中に存在するサービス等であっても、その申請者にとってはまだ開始していない事業であれば、上記の定義に該当する限り、新事業活動にあたります。(参考:経済産業省 経済産業政策局 新規事業創造推進室「グレーゾーン解消制度」、「規制のサンドボックス制度」及び「新事業特例制度」の利用の手引き)。
たとえば、ある電子契約サービスが電子署名法第2条第1項の「電子署名」に該当することを確認する申請(より正確には、国や地方公共団体の契約書においても使用可能な電子署名は電子署名法上の電子署名に限るという規制があり、自社サービスがこの電子署名であるかを確認する申請)は、2021年以降、複数の事業者が行っています(参考:デジタル庁ウェブサイト)。電子契約サービス自体はすでに目新しいものではありませんが、自社にとっては新たな事業であるという場合には、過去の申請者と同様に、自社サービスが「電子署名」に該当することを確認することができます。
逆に、申請前にすでに開始してしまった事業については、対象外となるため注意が必要です。
2 確認対象となる「規制」
確認対象となる「規制」がどのような法令を指しているのか、産業競争力強化法上は明確な定義がありません。もっとも、経済産業省の発行する『規制対応・規制改革参画ツールの活用に関するガイダンス』(こちら)では、「規制」とは「公益の実現を図るために、国や地方公共団体が企業や個人の権利を制限し、又はこれに義務を課す作用を持つもの」と定義されています。あえて誤解を恐れずに言えば、企業や個人の活動を制限する可能性のある法令が「規制」であると考えてよいでしょう。
グレーゾーン解消制度で適用の確認が可能なのは、「規制」に限定されています。例えば、先ほどの電子署名法の「電子署名」の例では、第2条第1項の電子署名という定義だけでは、企業や個人の活動を制限する法令とはいえず、「規制」には該当しません。しかし、電子署名の定義を引用する契約事務規則や地方自治法等が、「電子署名」に該当しなければ国や地方公共団体の契約書の記名押印に用いることができない、という「規制」をかけているため、この規制の対象となるかを確認すれば、おのずと「電子署名」に該当することが確認できるというロジックとなっています。
そのため、申請の際には、自社の事業がどの法令によってどのように事業活動を制限されているのか、慎重に検討する必要があります。
3 申請の流れ
一般的な申請の流れは、以下の通りです(以下の通りに進まない可能性もあることをご了承ください。)。
(1) 経済産業省経済産業政策局産業創造課へ連絡し、事前相談を行う。
(2) 経済産業省のサポートのもと、申請書(照会書)を作成する。
(3) (2)と平行して、経済産業省は申請の対象となる規制を所管する省庁と協議を行い、申請がされた場合の当該規制所管省庁の回答内容を事前に検討する。
(4) 申請者、経済産業省、規制所管省庁の間で、回答内容を確認し合う。
(5) 回答内容を確認したあと、申請者が、正式に照会書を提出する。
(6) (5)から約1か月後、規制所管省庁が正式に回答を行う。
グレーゾーン解消制度の回答までの期間は「1か月以内」であると説明されることが多いのですが、これはあくまで上記の(5)から(6)までの期間にすぎません。申請内容や事業者側の整理の進み具合によっては、事前相談の期間に数年を費やすこともあり、注意が必要です。
第3 おわりに
グレーゾーン解消制度を用いることで規制への対応が不要と判明すれば、不要な規制対応コストをカットできることがあります。逆に、規制に則した事業であることが担保されれば、そのこと自体に広告的価値が生まれることもあります。
当事務所では、グレーゾーン解消制度について実際の申請経験を有する弁護士が、申請の検討からお手伝いさせていただきます。新規事業の検討にあたり各種規制についてご不明点がある場合を含め、ぜひ当事務所にご相談ください。