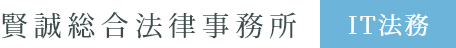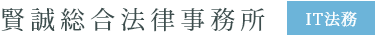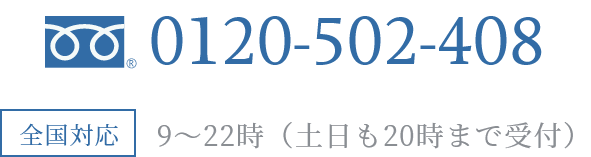通信販売の申込み段階における表示についての特定商取引法上の留意点
- ECビジネス
- 特定商取引法
弁護士: 松井立平
1 はじめに
近年、インターネットを通じた通信販売(EC)については、手軽に商品を購入できる利便性の一方で、「お試し」のつもりが定期購入になっていた、解約方法が分かりにくいといった消費者トラブルも後を絶ちません。こうした状況を受け、特定商取引法(以下「特商法」といいます。)では、消費者が最終的に申込みの内容を確認し、意思表示をする段階での表示について、事業者に一定の義務と禁止事項を定めています 。今回は、消費者庁が公表している「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」 を参考に、通信販売の申込み段階における表示についての特商法上の留意点を解説します。
2 対象となる「特定申込み」について
特商法第12条の6が規律するのは、「特定申込み」と呼ばれるものです 。具体的には、以下の2つのケースが該当します。
- 申込書面による申込み: 事業者が用意した申込用はがきや申込用紙など、所定の様式の書面を用いて消費者が行う申込み 。
- インターネット通販等における最終確認画面での申込み: いわゆる「最終確認画面」など、事業者が表示する手続に従って消費者が申込みボタンなどをクリックすることで契約申込みが完了する画面での申込み 。
電話での申込みなど、最終的な申込み段階で事業者が用意した書面や画面を利用しない場合は、原則として特定申込みには該当しません 。
本コラムでは、主に最終確認画面における表示の留意点について解説いたします。
3 最終確認画面等で表示すべき事項(法第12条の6第1項)
特定申込みに該当する場合、事業者は最終確認画面に、以下の事項を表示する義務があります 。
- 分量: 商品の数量、役務の提供回数・期間など 。定期購入契約の場合は、各回の分量に加え、引渡しの回数や総量も表示する必要があります 。無期限契約の場合はその旨と、目安となる期間の分量を示すことが望ましいとされています 。
- 販売価格・対価: 送料が含まれない場合は、販売価格と送料の両方を表示する必要があります 。定期購入契約の場合は、各回の代金に加え、支払総額も明確に表示しなければなりません 。無償期間や割引期間がある場合は、有償・通常価格への移行時期や金額も明示が必要です 。
- 支払の時期・方法
- 引渡・提供時期
- 申込みの期間に関する定め: 期間限定販売など、申込みができる期間に定めがある場合は、その旨と具体的な期間を表示する必要があります 。「今だけ」のような曖昧な表示は認められません 。
- 申込みの撤回・解除に関する事項: 解約の条件、方法、効果などを表示します 。定期購入契約で解約申出に期限がある場合や、違約金が発生する場合は、その内容も表示が必要です 。返品特約についても表示が求められます 。特に、解約方法が限定されている場合(例:電話連絡のみ、特定の時間帯のみ)は、最終確認画面で明確に表示することが求められます 。
これらの表示は、原則として最終確認画面等に網羅的に表示することが望ましいですが、スペースの制約等から難しい場合は、消費者が明確に認識できることを前提に、参照箇所を明記して広告の該当箇所等を参照させる形式も許容されています 。ただし、リンク先等で容易に認識できるよう表示されている必要があります 。
4 禁止される表示(法第12条の6第2項)
以下の表示は禁止されています。
- 申込みとなることを誤認させる表示: 「無料プレゼント」などの表示を強調し、有償契約の申込みであることが分かりにくい表示や 、クリックすると申込みが確定することが明確でないボタン(例:「送信する」「次へ」のみ)などが該当するおそれがあります 。
- 表示事項について誤認させる表示: 表示事項自体は事実であっても、その表示位置、形式、文字の大きさ、色調などにより、消費者に内容を誤認させるような表示です 。例えば、定期購入契約において、初回価格のみを著しく目立たせ、契約期間や支払総額、解約条件などを小さな文字で分かりにくい場所に表示するケースが考えられます 。特に、「お試し」「トライアル」「いつでも解約可能」といった表示は、消費者に誤解を与えやすく、実際の契約内容と異なる場合は違反となる可能性があります 。
5 顧客の意に反する申込みを誘引する行為の禁止(法第14条第1項第2号)
インターネット通販において、消費者が申込み内容を容易に確認・訂正できるようにしていないことは、禁止行為とされています(特商法施行規則第42条第1項) 。
具体的には、最終確認画面で注文内容が容易に確認できない場合や、「変更」「戻る」ボタンがないなど訂正する手段が提供されていない場合が該当するおそれがあります 。また、消費者が自分で変更しない限り定期購入となるように初期設定されているなど、意図せず不利な契約を結ばせてしまうような画面設計も問題となる可能性があります 。
6 まとめ
通信販売、特にインターネット通販においては、最終確認画面の表示について特定商取引法の規制を遵守する必要があり、専門的知見が必要となりますので、弁護士への相談をおすすめいたします。